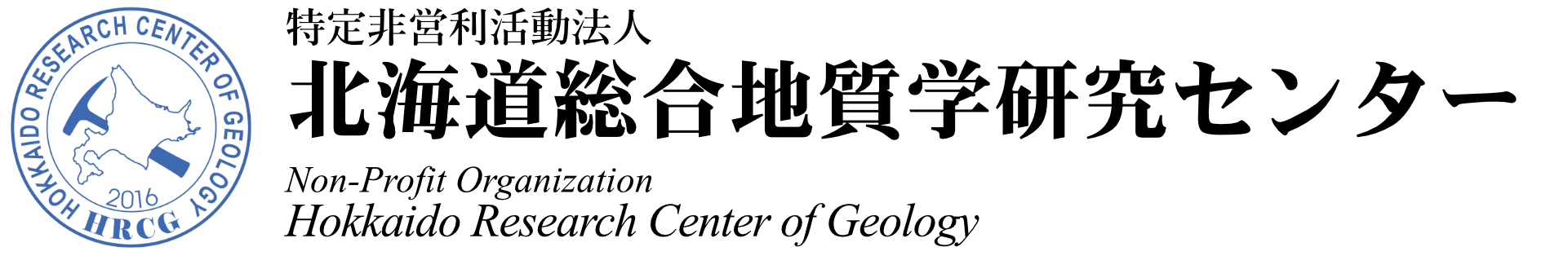

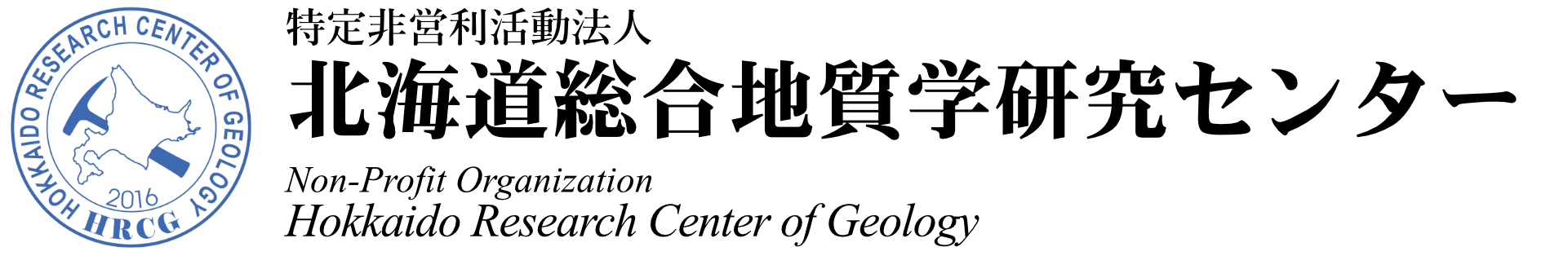

2018年胆振東部地震における地盤変動(災害)は斜面堆積物の崩壊が発生件数の圧倒的多さから注目されてきた. しかし, 地下深部の地震断層の動き(地震動)は断層の上位の地表部に岩盤崩壊をあちこちで出現させている. 公開シリーズとして, 岩盤崩壊を地域毎に順次報告するが, 今回はその第2回目として崩壊分布域中央部「幌内地域およびシュルク沢・オコッコ沢・東和川上流域」について取り上げる.
個々の崩壊地については, 公開データ(国土地理院・グーグルマップ空中写真および北海道の航空レーザー測量データ)により, 平面写真および 1 mコンター地図・断面図で表現するとともに, 現地写真でも紹介する.
その1 [PDF link]
その2 [PDF link]
その3 [PDF link]
私たちは石狩低地研究会の一員として2012年以来, 厚真川下流低地の沖積層の研究を進め, 同上流域の厚幌ダム工事関連遺跡調査に関わり段丘や火山灰の調査を行ってきました. そういう中で発生したのが2018年胆振東部地震でした. 地震発生前から地形・地質の調査を続けてきた者として, 責務のようなものを感じて, 地震による地盤変動と災害の実情を調査し2年が経過しました. 本シリーズでは地震断層の動きとそれによる地震動をストレートに反映したと考えられる岩盤崩壊の実体について解説付き写真集で紹介します.
その1 胆振東部地震の岩盤崩壊について: 導入的説明1~6 [PDF link]
その2 岩盤崩壊についての地域毎の説明:ショロマ西岸の岩盤崩壊 [PDF link]
株式会社北海道技術コンサルタントのホームページに技術報告書(PDF)として掲載されています.震源近傍地域に存在する活断層や大規模斜面崩壊などについての現地調査に基づく貴重な資料が多数掲載されています.
Yamagishi, H. and Yamazaki, F. (2018) Landslides by the 2018 Hokkaido Iburi-Tobu Earthquake on September 6.
Landslides, Vol. 15, Issue 12, 2521–2524. [link]
Abstract
In the early morning of September 6th, 2018, an intense earthquake struck Hokkaido Iburi-Tobu area. By this earthquake, many landslides occurred and claimed 36 lives. The landslide numbers reached 6,000 and mostly they are shallow landslides moving down of the air-fall pumice layer from Tarumai volcano which erupted ca. 9,000 years ago. However, southeast of the area, deep-seated landslides of dip-slipping type are also found.
Keywords
Intensive earthquake Landslides Hokkaido Japan
岡 孝雄 (当研究センターシニア研究員)・関根達夫 (当研究センターシニア研究員)・山崎芳樹 (当研究センター研究員) ら 石狩沖積低地研究会 による 厚真町管内での地形・地質状況緊急調査の 2回目の報告.
岡 孝雄 (当研究センターシニア研究員)・関根達夫 (当研究センターシニア研究員)・山崎芳樹 (当研究センター研究員) ら 石狩沖積低地研究会 による 厚真町管内での地形・地質状況緊急調査の報告で, 今回の平成30年北海道胆振東部地震によって新たに出現した活断層や崩壊の報告を含む.
Yamagishi, H. and Iwahashi, J. (2007) Comparison between the two triggered landslides in Mid-Niigata, Japan by July 13 heavy rainfall and October 23 intensive earthquakes in 2004. Landslides, Vol. 4, 389–397. [link]
山岸宏光・斉藤正弥・岩橋純子 (2008) 新潟県出雲崎地域における豪雨による斜面崩壊の特徴 -GISによる2004年7月豪雨崩壊と過去の崩壊の比較-. 日本地すべり学会誌, 45巻 1 号, 57–63 頁. [PDF link]
佐藤 浩・小荒井 衛・宇根 寛・岩橋純子・宮原 伐折羅・山岸宏光 (2007) 平成19年(2007年)新潟県中越沖地震による斜面崩壊の地形的特徴のGIS解析. 国土地理院時報, 2008 114集, 91–102 頁. [PDF link]
Iwahashi, J., Kamiya, I., and Yamagishi, H. (2012) High-resolution DEMs in the study of rainfall- and earthquake-induced landslides: Use of a variable window size method in digital terrain analysis. Geomorphology, Vol. 153–154, 29–38. [link]
山岸宏光・土志田 正二・畑本雅彦 (2016) 最近の豪雨崩壊および既往の地すべりにおける地形・地質要因のGIS解析. 地すべり学会誌, 52巻 6号, 282–292 頁. [PDF link]
この論文の著者である田近 (当研究センター会員) によると, 厚真町の厚幌1遺跡の約4000年前の地すべりが, 今回の胆振東部地震によって発生した地すべりと極めて類似するメカニズムによって発生しており, またその年代が石狩低地東縁断層帯馬追断層の最新活動期と重なる. 今回の地震とその災害を検討する上で重要な論文であると考えられる.
記事の概略は以下の通り:厚真では これまで未確認であった断層が少なくても 4 カ所存在する可能性が岡らの調査で判明. 岡は, 今回の地震の震源は約 37 km と 大変深いので, 地表で観察されるこれらの断層と震源との直接の関連は考えにくく, 周辺で地震が繰り返されたことによって地表部の地層が変形した "副次的活断層" の可能性を指摘. 今回の地震と「石狩低地東縁断層帯」との関連も政府地震調査委員会で見直されており, 岡は「地表に現れ,詳しく調査されている活断層はごく一部で, 多くは見過ごされている. 活断層は身近に存在すると再認識する必要がある」と指摘.
石狩沖積低地研究会によるこの報告内容の説明
今回の調査は9月13日の第1回目に続く第2回目である. 主目的は厚真川中流域の富里より上流の台地・丘陵・山地域において多発した崩壊現象について, 観察・写真撮影を行うことである. 前回の調査では桜丘・東和・吉野・富里地域においては活断層とその可能性のあるリニアメント沿いでの地震後の変状把握を主目的としたが, 結果的にはその可能性が低いことを把握した. そのため, 富里より上流地域については, そのテーマは付随的なものにとどめた.
報告のとりまとめにあたり, 国土地理院が9月6日および9月11日に撮影した空中写真, 地震調査研究推進本部・産総研地質調査総合センターなどの公表資料を利用し, 解析の一助とした. なお, 今までの2回の調査だけでは全容把握とはいかないため, 今後も機会を得て調査を継続したいと考えている.
石狩沖積低地研究会によるこの報告のまとめ
① 低地・台地(T2面)では埋設水路管のコーナー部などでの地震動にともなう破断(または分離)による陥没や噴砂などの現象, 地形変換部での路盤上の亀裂, 路肩沿いの亀裂, 橋梁への道路連結部での段差の発生など, 人工物に関連した現象は多くみとめられたが, 活断層またはリニアメントに沿う, 断層活動に直接起因する変状は認められなかった.
② 富里西方活断層露頭(地点11)では新たな活断層露頭が今回の地震により出現した. その観察から, この活断層(N8°W方向のリニアメントに一致)は, 東落ち高角度の階段状断層で, Ta-d(9,000年前頃降灰)基底面の総計の落差(オフセット)は約 5 mである. Ta-c(3,000年前頃同)も変位を受けるが, Ta-b(1667年同)は地形なりに断層を覆っており, 切られていない. よって, 9,000年前以降2回以上の断層活動があった推定される. 新活断層露頭は今回の地震で滑落崖の役割を果たし, 前面には地すべり性地割れ・ブロック群が存在し, リニアメントに沿って北へ延長すると, 崩壊が発生しており注目される. 活断層であることが明瞭となったことから,「吉野断層」という固有名をつけて今後取り扱う. 北方延長部を含めて今後の精査が必要である.
③ 活断層関連で地点 1, 2, 5, 11 および地点 10 付近で地震にともなう崩壊現象を観察できた. 地震後撮影の空中写真の判読を含めて判断すると, 大部分のものは, 斜面を覆う堆積物が瞬時の大きな地震動(最大深度 7)で不安定となり堆積物が上を覆う樹木毎ブロック状に崩壊し, 地すべり的に流動したものである.
④ 崩壊対象の斜面堆積物は火山灰(Ta-d・Ta-c・Ta-b)と, それらの前後のローム層, 腐植土層がサンドイッチ状に重なったものであり, 1 万年近い時間経過で堆積したものである. T4 面(中位段丘 3 面)および T5 面(高位段丘面)では, このような時間経過の堆積物の下位に5~1万年前間の火山灰(Kt-1・Spfa-1・En-a)とそれらの前後のローム層, 腐植土層が重なった堆積物がともなわれており, それらを含めて, 段丘末端崖で崩壊に巻き込まれた事例もある.
⑤ 富里北東部で認められた崩壊・地すべりは, A:平滑斜面での崩壊, B:落差のある沢斜面のほぼ全体に崩壊が発生し谷底に長い舌状体が形成, C:沢奥での発生がなく谷底に長い舌状体形成されない, D:平滑斜面とスプーン状浅谷での瀑布状の崩壊などが認められた. このように, 今回の地震で発生した膨大な数の崩壊地形は様々なタイプが認められ, それらは今後調査・検討が行なわれるであろう.
⑥ 石狩沖積低地研究会2012年~2017年の6年間, 厚真川流域で, 既存地質資料の入手・解析と共に, 河川改修関連のボーリングコアの解析(下流域), ピートサンプラーによるコア採取とその分析および既存露頭の観察(中流域), ダム建設関連の露頭・遺跡発掘での地質観察(上流域)などを行い, 沖積層や過去6万年前以降の段丘堆積物の検討を行ってきた. 上流域の厚幌ダム地域の調査・地形解析では, 現氾濫原面, 段丘面(9,000年前頃以降形成のT0~T2面)上に, 小扇状地(いわゆる沖積錐)が多数存在するのを確認しているが, それらは, 流水の作用だけでなく, 今回のような地震による崩壊に起因があるものが存在する可能性がある. それにしても, 大量に樹木を含むような堆積物は今のところ確認はされていない. もしそのような堆積物が存在しないとすれば, 今回のような崩壊現象は過去1万年間にも生じていないことになるが, はたしてどうであろうか. そのような視点での調査・検討も必要であろう.
⑦ 斜面や台地末端での崩壊に関わって, 今後, 斜面や河岸段丘面(台地)の区分や, 関連堆積物の構成が問題となる. 厚真川上流域については, 厚幌ダム地域での遺跡発掘に関連して, 地形面分布と地形面毎の堆積物の内容が体系的に明らかにされている. 中流域でのそのような把握の参考になると思われるが, それについては, 次回の報告で示したい.
広く市民の皆さまから提供していただいた 土砂崩れ, 道路の地割れ, 道路の陥没, 墓石の倒壊など, 身近なところで観察された地震による地学的被害状況のレポートを掲載し, 記録に残したいと思います. 観察地点の位置を示した地図, あるいは緯度・経度 (スマートフォンの地図アプリなどでわかります) を添えて, 数枚以下の写真ファイルとともに簡単な説明文を office@hrcg.jp までお寄せください. なお, 掲載の可否は HRCG で決定させていただきますのでご了承ください.
2018年9月6日午前 3時 8分, 北海道は胆振地方を震源とする極めて強い地震 (平成30年北海道胆振東部地震) にみまわれ, 大変深刻な災害を被りました. 北海道総合地質学研究センター構成員一同, 不幸にしてなくなられた方々にお悔やみを申し上げるとともに, 被害を受けられた多くの方々に心からお見舞い申し上げます.
北海道総合地質学研究センターは地質学の専門家を含む集団ですので, 今回の地震とその災害に関する有益な情報を発信したいと考え, 平成30年北海道胆振東部地震特設ページを開設いたしました. なお,この特設ページに掲載された署名付きの文章は執筆者個人の知的所有権に属し, もちろん執筆者の個人的な見解であり, 特定非営利活動法人 北海道総合地質学研究センターの見解ではございません. この特設ページに関する ご意見・ご要望がございましたら office@hrcg.jp までお寄せください.
平成30年北海道胆振東部地震とそれに伴う災害に関する情報リンク